世界で働く
日本人職員


©Megumi Iizuka
8年にわたる紛争で人道危機に陥っているイエメン。経済は崩壊、社会的支援システムは機能不全となり、子どもたちはきびしい状況におかれています。220万人の子どもが栄養不良になり、そのうち54万人以上が重度の急性栄養不良(緊急に治療を受けなければ命にかかわる状態)に苦しんでいます。
紛争しか知らずに育つ子どもたちへ平和な未来への希望をつなぐべく、ユニセフは現地で活動を続けています。
こうしたイエメンの現状を、広報・アドボカシー部門のチーフとして日夜発信し続ける飯塚の一日をご紹介します。
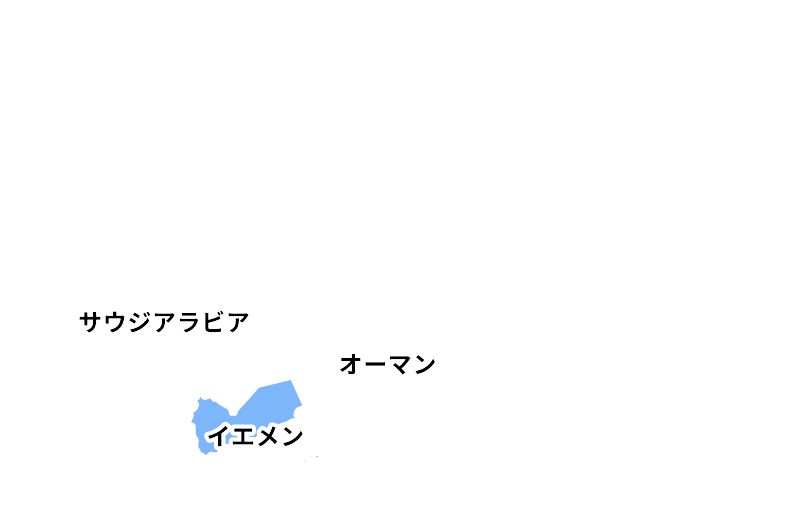
長引く紛争の影響で、イエメンでは人口の6割以上が人道支援を必要としています。地雷や不発弾によって命を落とす子どものニュースも絶えません。広報チームは、ユニセフが実施しているさまざまな支援活動を記事、動画、写真などを通じて広めます。報道機関への働きかけも行います。
人道支援の現場に身を置きたくて、2023年8月に今のポジションに応募し転職しました。ただ、政府の規制や自粛でここ数年北部では広報の取材はすべて外注、現場にほとんど出ていないという事実を知りました。なんとか状況を変えたくて代表や事務所に掛け合い、赴任して2カ月目にようやくサウジアラビアとの国境付近の山奥の村で取材が叶いました。


空爆で崩れた橋をよけ、道のない山肌をランドクルーザーで7時間揺られて到着した集落では地下水がなく、雨水に頼っていました。衛生状況も劣悪でコレラが蔓延、女性や子どもは遠くまで水を得るため多くの時間を費やしています。ユニセフは安全な雨水濾過タンクを設置したところで、住民の生活改善が期待されています。
帰り道には、空爆で2階の天井や壁が崩れ雨ざらしとなった集落の学校を訪れました。5教室しかない小さな校舎で午前と午後の入れ替え制で800人が今もここで勉強をしています。立ち寄った時はすでに放課後でしたが、近所から子どもが来ていて、机も椅子もないから、水で濡れて穴の開いたコンクリートの床に直接座って勉強していると話してくれました。
ユニセフは空爆の被害にあった学校の修復も行っていますが、まだまだ支援を届けられずにいる地域がたくさんあります。こうした現状を伝えることで支援の輪を広げることに貢献できればと思います。
イエメンは治安状況から家族帯同ができません。8歳の娘を日本に残しての赴任には迷いもありましたが、ずっと希望していた現地での活動を全面的に応援してくれた夫と娘には感謝しています。



「出前」も楽しめます!
バーミヤンとよばれるオクラとトマトなどの煮込み料理とチキンとライス。戦争で職をなくした女性が自宅で始めたというケータリングサービスを同僚とオフィスで注文
※データは主に外務省HP、『世界子供白書2021』による
※地図は参考のために記載したもので、国境の法的地位について何らかの立場を示すものではありません
埼玉県加須市出身。早稲田大学国際教養学部卒。ロンドン大学高等研究院難民保護・強制移住修士号取得。報道機関で英文記者として勤務した後、トルコ・イスタンブールのUNWomen地域事務所でシリア難民女性の支援に従事。国連WFP広報官を経て2023年8月より現職。