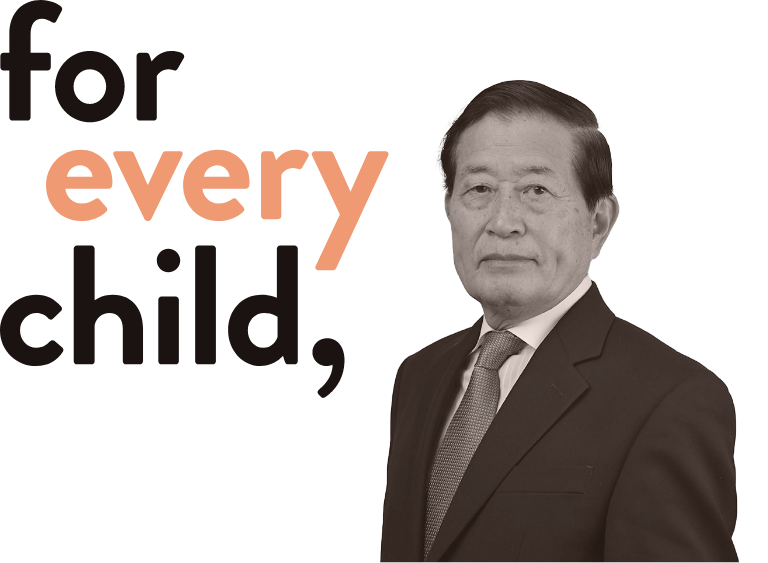
各界で活躍されている方に「子ども時代」を振り返っていただきながら、世界中のすべての子ども、一人ひとりの子どもたちにとって必要なことは何かを考えていく連載企画「for every child,_」。第30回は、子どもや女性をはじめすべての人の命、生活、尊厳を確保する「人間の安全保障」を、長年にわたり推進してきた当協会の高須幸雄会長です。外交官として国連大使などを歴任し、事務次長など国連事務局幹部として、長く国際協力の現場に身を置いてきた高須会長。日本の戦後の庶民生活が浮かぶ思い出とともに、多様な文化への敬意と子どもに向けられたやさしいまなざしが感じられるメッセージを寄せました。
私は子ども時代、横浜で育ちましたが、当時は戦争の傷跡が大きく残っており、駐留兵や駅頭に立つ傷痍軍人から、戦争の悲惨さ、平和の大切さを感じる毎日でした。救援物資の脱脂粉乳から温めたミルクを給食で飲んで育ったので、ユニセフのために働ける機会をとてもうれしく思います。
そんななかで、子ども時代の楽しい思い出は遊びでした。とても遊び好きな浜っ子で、キャッチボール、かくれんぼ、縄跳び、缶蹴り、竹棒など身近にあるものを使って男女を問わず仲よく遊んでいました。特に好きだったのは、大桟橋に停留する外国客船を眺めながら、友達と一緒に釣りをすることでした。地元ではお祭りが盛んで、神輿を担いで町内を練り歩いたものです。
当時、海外からの主たる玄関口は横浜港でしたから、大型客船が着くと大勢の外国人(主に米国人)が市内を歩き回り、外国を感じることが出来ました。記憶に強く残っているのは、横浜開港記念の「港まつり」の行列が中心部を練り歩いて我が家の前を通過する際に、行列のなかの着飾ったチマチョゴリの女性が大勢トイレを借りに我が家に駆け込んできたことです。異なる文化の存在を身近に感じた瞬間で、海外への好奇心を高めてくれました。
このためか、小学生の頃から将来は海外と関係する仕事をしたいと思いはじめました。はじめの夢は客船の船長になることでしたが、水泳が苦手なので外交官になって戦争のない世界をつくりたいと思い直し、結局その夢がかないました。
最近、各地の小中学校で子どもの権利条約の出前授業をする機会が増えました。
子どもの権利のなかで私が好きな権利のひとつが「遊ぶ権利」(第31条)です。子どもたちからはほんとうにそんな権利があるのか? と聞かれますが、「学ぶ権利」と同じくらい、「休む権利」「遊ぶ権利」が子どもが健やかに育つためには欠かせないのだと説明すると、その顔が輝き、安堵する様子がうかがえます。
日本冒険遊び場づくり協会の天野秀昭さんは、「子どもにとって遊ぶとは、自分の世界の構築を意味しており、自分自身の核をつくるうえでは不可欠な経験だ」と言われています。すべての子どもが子どもらしく楽しくすごし、持っている可能性を最大限伸ばせるよう、「遊ぶ権利」を大切にしていきたいと思います。

神奈川県出身。1969年外務省入省。国連外交の分野で長い経歴を有する。国連政策課長、国際社会協力部長、在ウィーン代表部常駐代表、国連代表部常駐代表(2007-10年)を歴任。国連事務局では、事務次長補(1993-97年)、事務次長・行政監理局長(2012-17年)を歴任。現在、事務総長特別顧問(人間の安全保障担当)、NPO法人「人間の安全保障」フォーラム理事長。2019年より公益財団法人 日本ユニセフ協会副会長。2024年2月当協会の会長に就任。