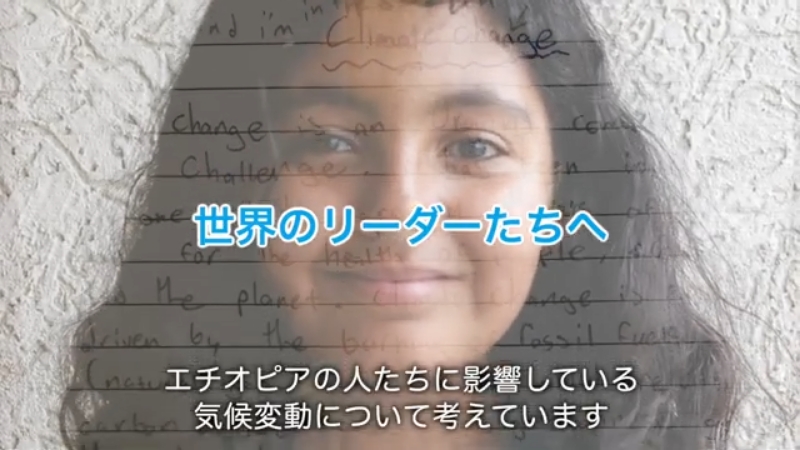© UNICEF/UN0836942/Naftalin
特集
地球は子孫から借りているもの
気候変動と子どもたち
観測史上もっとも暑い夏となった2023年は、
世界各地で自然災害が多発しました。
今年の夏も記録的な猛暑が予測されています。
もはや待ったなしの気候変動問題。
その影響で、世界の子どもたちも、
さまざまな危機に直面しています。
気候変動は地球環境と、子どもたちのいまと未来を変えているのです。
しかし現状の対策は、あまりにも子どもたちに注意が払われていません。
子どもたちに重点を置いた気候変動対策になるよう
取り組むユニセフの活動をご紹介します。
負うべきではない重荷
近年、パキスタンの大洪水、サハラ以南のアフリカでの歴史的な干ばつとその収束後に起こった大洪水、ヨーロッパと中東の一部での猛烈な熱波、カナダやハワイでの山火事など、気候変動に起因する大災害が相次ぎました。日本でも、各地での記録的な大雨や観測史上もっとも暑かった昨年の夏などは記憶に新しいところです。
私たちの世界はすでに気候変動の影響によって破壊と荒廃が進みつつある─そんな衝撃的な事実が、気候変動に関する国際的な報告書(*1)からも明らかになっています。

2022年6月から10月にかけて発生した洪水によって1,739人の命がうばわれました
© UNICEF/UNI431676/Sokhin
こうした災害や異常気象はいま、世界各地で、人道危機をより深刻化させています。干ばつによる食料不足が引き起こす子どもたちの栄養不良、水不足からくる衛生環境の悪化で流行するコレラなどの感染症、さらに、洪水や干ばつで故郷に住めなくなった人々が大移動する「気候難民」という新たな問題も起こっています。また、以前から水不足に悩まされていた地域では、水資源をめぐる地域間紛争のリスクも高まっています。実際、近年の国連の人道支援要請の4分の3以上が異常気象に関連しており、2000年の3分の1から大きく増加しています。
今後数十年間で気候変動がさらに進めば、私たちがいま享受している命と健康、水と食料、自然環境に重大な影響がおよぶことは明らかです。その結果、もっとも苦しむのは、その先の未来を生きる子どもたちです。2050年までに発生する気候変動のほとんどは、これまでに放出された温室効果ガスによるものといわれています。産業革命以来、前世代が積み重ねた排出物が原因の気候変動で、本来はその責任がないはずの未来を生きる子どもたちが不当に大きな重荷を背負わされるのです。
*1…気候変動に関する政府間パネル(IPCC)による第6次評価報告書統合報告書
子どもたちの声が届かない
重荷を背負わされているのは、いまを生きている子どもたちも同様です。ユニセフの報告書(*2)によれば、現在すでに世界22億人すべての子どもたちがなんらかの形で気候・環境危機にさらされています。なかでも半数にあたる約10億人は、自然災害の影響を受ける可能性が高く、その危機に対処する基本的な社会サービスも不十分な、「極めてリスクが高い」33カ国のいずれかで暮らしています。
国や地域に起因するリスクに加え、子どもたち特有の脆弱性がもうひとつあります。それは、発達段階にある子どもは、気候変動による環境悪化の影響をおとなより強く受けてしまうことです。子どもの心身は、汚染された空気、極度の暑さ、栄養不足にとりわけ脆弱なため、気候変動によって本来の成長を妨げられるリスクにもさらされているのです。

学校が大好きで、教師になりたいと思っています(エチオピア)
© UNICEF/UNI485924/Pouget
このように二重の脆弱性を負っている子どもたちの視点は本来、気候変動対策の中心に据えられるべきです。しかし残念なことに、往々にして軽視されているのが現状です。ユニセフの調査報告書(*3)によると、世界の主要な気候変動問題対策資金(気候資金)のうち、子どもに対応した活動を支援していると分類できるのは、わずか2.4%にすぎないことがわかっています。ユニセフとともに子どもの権利を守るための活動をしているカリブ海の島国バルバドス出身の11歳のマリアさんはいいます。
「子どもは、世界の未来を担います。でも、私たちの未来は、現在意思決定をしているおとなたちの行動によって形作られていて、私たちの声が届いていません。気候変動対策には、子どもたちのニーズと視点がふくまれていなければならないと私は思います」
*2…報告書『気候危機は子どもの権利の危機』(2021年 ユニセフ)
*3…調査報告書『不足への取り組み:子どものための気候ファイナンス』(2023年 ユニセフ)
ユニセフの気候変動対策
今後30年間で約42億人の子どもが誕生すると予想されるなか、生まれくる子どもたちのために気候変動に「備える」ことは、いまを生きる私たちの責任です。ユニセフは、すべての人にとって住みやすい未来をつくるため、国際社会やそのリーダーたちに、いまを生きる子どもたちと将来生まれてくる世代を気候変動対策の中心に据えることを強く求め、世界各地でさまざまな活動をおこなっています。

© UNICEF/UNI419968/Preechapanich
2023年11月末から中東の都市ドバイで開催された第28回気候変動枠組条約締結会議(COP28)では、気候変動が子どもたちの健康とウェルビーイング(幸福や充足)におよぼす影響に国際社会の注目を集める取り組みをおこないました。また、保健、教育、水と衛生など子どもたちに必須の社会サービスについて、気候変動への耐性を強化しなければならないという点についても、会議に参加した世界各国の関係省庁に働きかけました。さらにユニセフはCOP28に向けて、次の3つの目標を掲げた「持続可能性と気候変動に関する行動計画」をまとめました。
1 プロテクト(保護する)
気候変動対策には大きく分けて、その原因となる温室効果ガスの排出量を減らす「緩和」策と、すでに生じている(あるいは将来予測される)被害を回避・軽減させる「適応」策のふたつがあります。ユニセフが掲げる「プロテクト(保護する)」は、地域社会の子どもにとって必要不可欠な社会サービスを、気候の変化、災害の頻発化、環境の悪化に「適応」させ、子どもたちの生活と健康、そして地域社会の回復力を守ることを目標にしています。主には、子どもたちにとって必須の医療施設、学校、給水設備、栄養サービスなどを気候変動に強く、環境にも配慮した持続可能なものにすることなどがあります。

マダガスカルでは何年も続く干ばつで農作物は枯れ、深刻な食料不足に直面しています
© UNICEF/UNI419329/Prinsloo
一例をあげると、2023年、ユニセフ・ベネズエラ事務所は、浄水場を修復して太陽光発電式のシステムにすることで、5つの州で計25万人以上が安全な水を使えるよう支援しました。デルタアクマロ州の州都からボートで6時間離れたサンフランシスコ・デル・グアヨの先住民コミュニティでは、住民は川からの未処理の水を飲用水や生活用水としてそのまま利用していました。水の利用は天候に左右され、衛生面でも大きな懸念がありましたが、太陽光発電式の浄水場となったことで、温室効果ガスの削減に貢献しながら、異常気象でも安全な水を使用できるようになりました。この浄水場は近隣の村をふくむ1200人以上に安全な飲料水を提供。保健センターの水質も改善され、安全な出産やより良い母乳育児の実践、入院が必要な子どもたちへの安全なケアも可能になりました。水道の改善にあわせ、衛生促進活動も地域全体で実施され、子どもたちの感染症も防ぐことができています。
2 エンパワー(力を与える)
次は、気候変動の最大の当事者である子どもと若者を「エンパワー(力を与える)」する目標です。子どもや若者は、おとなが地球の危機を解決してくれるのを待つだけの存在ではなく、当事者として、環境保護活動を推進し、政策立案にも関わり、社会に訴える声をあげるだけの力を持っています。

© UNICEF/UN0403958/Franco
ユニセフは、ボランティア活動、アドボカシー(政策提言)活動、起業、持続可能な経済活動を可能にするグリーンスキルの習得といった活動を通じて、子どもと若者の力を引き出し、気候変動に立ち向かう変革の担い手として活動できるよう取り組んでいます。(本号のunicef fileやfaceでも事例をご紹介しています。ぜひご覧ください)。
たとえば、過去10年間で干ばつが7倍、洪水とサイクロンが6倍に増加している、ムンバイ市を擁するインドのマハラシュトラ州(マハ州)では、若者たちが気候変動に関する知識を得て、変化の担い手として自ら活動できるよう、MYCA(マハ州の若者たちによる気候変動活動)という取り組みを展開しています。これは、気候変動関連のさまざまな研修や環境教育を提供するもので、これまでに280万人の若者、46万5千人の子ども、1万人以上の教師が受講しました。この取り組みの一環で、500人以上の若者がユース・アドボケーター(若き提唱者)として州レベルの気候変動関連の政策会議に参加し、意思決定者に若者たちの声を届けるとともに、地域社会の意識も高めています。
3 リデュース(削減する)
最後は、人道支援や社会サービスの提供などユニセフ自身の活動で排出される温室効果ガスなどの環境負荷を「削減」していく目標です。

避難所にもなりますが、地下水位が高いため、豪雨の際は校庭が水浸しになります
© UNICEF/UNI485832/Bak Mejlvang
国連組織のなかで最大規模で支援物資やサービスを調達するユニセフは、たとえば2017年以降、15万台以上の冷蔵庫を調達して支援国に納入し、10億人近くの人々に恩恵をもたらすコールドチェーン(ワクチンの保冷輸送)を維持しています。ユニセフはこうした機器に長く継続使用できるものを選び、現地で使用する電気についても太陽光発電式に切り替える動きを主導しています。ほかにも、社会サービスの提供におけるさまざまな調達を可能なかぎり地元でおこなうようにしたり、保健センターや学校の建設時に持続可能で革新的な手法を試したりするなど、さまざまな取り組みをおこなっています。
たったひとつのもの
「この地球は先祖からゆずり受けたものではない。
未来の子どもたちから借りているものだ」
これは、アメリカの先住民のあいだで言い伝えられ、当協会の展示施設ユニセフハウス(東京都港区)にも掲げられている言葉です。地球は未来の世代から借りているものだとすれば、私たちはそれを彼らが住み続けられる惑星のまま、返さなければなりません。
若い世代の声は、気候変動問題に関する私たちの決定と行動の矢面に立つのが、私たちではなく、子どもたちであることを思い出させてくれます。人類は、肌の色、宗教、性別、そして、過去・現在・未来という世代を超え、たったひとつのものを共有しているのです。
だからこそユニセフは、未来の世代もここで住み続けられるよう、世界中で子どもたちを中心に据えた気候変動対策に取り組んでいます。

© UNICEF/UNI441013/Andriantsoarana